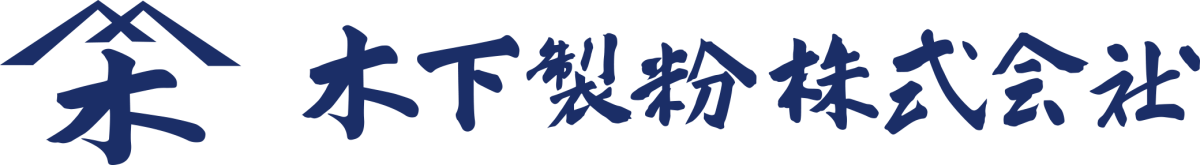#186 世界の製粉事情
 今時の製粉工場は、少しの小麦はなかなか製粉できないと、新着情報#185で説明しました。それは少ない小麦をちまちま挽いているのでは、生産効率が悪くビジネスとしては成り立たないからです。効率を優先すれば規模拡大しか選択肢はありません。反面どこもかしこも大工場になってしまったのでは、どこの小麦粉も金太郎飴みたいに特徴がなくなってしまい、更なるコスト競争が待ち構えていることになります。特徴をだそうとすればコンパクト工場は一つの方法ですが、それを市場が評価してくれるかどうかはまた別の問題です。
今時の製粉工場は、少しの小麦はなかなか製粉できないと、新着情報#185で説明しました。それは少ない小麦をちまちま挽いているのでは、生産効率が悪くビジネスとしては成り立たないからです。効率を優先すれば規模拡大しか選択肢はありません。反面どこもかしこも大工場になってしまったのでは、どこの小麦粉も金太郎飴みたいに特徴がなくなってしまい、更なるコスト競争が待ち構えていることになります。特徴をだそうとすればコンパクト工場は一つの方法ですが、それを市場が評価してくれるかどうかはまた別の問題です。
それはさておき、日本には製粉工場がいくつあるか想像してみてください。雲を掴むような話なので答を先に言うと、現在122工場(企業数は98社)あります。これが多いか少ないかは別にして、1950年には3,095工場、1965年には434工場あったことを思えば、かなり減ったことは事実です。これを踏まえるとこれからも減ることはあっても増えることはないはずです。また122工場と一口に言っても、その規模は千差万別で、一日に2000㌧以上の小麦が製粉できる工場がある一方、数㌧規模の工場もまだあります。
2000㌧の小麦といってもピンとこないと思いますが、これを製粉してできる小麦粉からは約1700万玉のうどんがとれるので、この工場が一週間も操業すれば、日本中の皆さんにうどん玉が行き渡る勘定になります。大規模製粉工場はこのくらい規模拡大が進んでいるのです。別の言い方をすると、この規模の工場が10工場もあれば日本の小麦粉需要は賄えることになります。では日本の製粉産業の集約度は世界的にみてどのくらい進んでいるのか?これについては次の表をご覧ください(かき集めてきたのでバラバラですが一応数年以内のものです)。簡単にまとめてみると:
| 国名 | 工場数 | 粉生産量(千トン) | 人口(万) | 年間消費量(kg) /人 |
工場数 /1000万人 |
生産量(千㌧) /工場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ |
196
|
18,296
|
30,500
|
60.0
|
5.54
|
108.3
|
| イギリス |
59
|
4,433
|
5,870
|
75.5
|
10.05
|
75.1
|
| フランス |
471
|
4,410
|
5,930
|
74.4
|
79.43
|
9.4
|
| ドイツ |
308
|
5,374
|
8,230
|
65.3
|
37.42
|
17.4
|
| イタリア |
332
|
4,250
|
5,874
|
72.4
|
56.52
|
12.8
|
| 日本 |
122
|
4,618
|
12,746
|
36.2
|
9.57
|
37.9
|
| 韓国 |
11
|
1,803
|
4,685
|
38.5
|
2.35
|
163.9
|
| 中国 |
50,000
|
77,000
|
131,397
|
58.6
|
380.53
|
1.5
|
①一人当たりの小麦粉消費量については、欧米は日本の約2倍。
②人口1000万人あたりの製粉工場数で比較すると、集約度が進んでいるのは韓国の2.35工場に対し、遅れているのは、中国の380工場。
③1工場あたりの製粉能力で比較すると、大規模化が進んでいるのは韓国の16.4万トン/年に対し、遅れているのはやはり中国の1500㌧/年。
この事実を勝手に解釈してみます。①については、日本人が小麦粉を嫌いではなくて、日本人は年間60kgのお米も食べているので、結構がんばっている方だと思います。実際、戦後(死語か?)は小麦粉消費が伸び続けたのに反し、お米の消費は減り続けています。②については、お隣の韓国がダントツなのは意外な気がするでしょう、きっと。これは日本に当てはめると四国(人口約410万)に製粉工場が1つくらいのカンジです。現在、四国には6つの製粉工場があるので、これから考えてもかなり集約されていることがわかります(余談ですけど、イギリス、フランス、イタリアって日本の半分しか人がいないのに、かなり存在感ありますよね)。
ただ人口換算では、一人当たりの小麦粉消費量に影響されるので、工場の規模を適性に比較するのであれば、一工場あたりの小麦粉生産量比較の方が正確にわかります(表右端)。しかしここでも集約化が進んでいるのは韓国で、1工場あたり年間16万トン生産しているのに対し、中国は僅か1500㌧と両者には100倍の開きがあります。二つの国は隣接しているにもかかわらず、これだけ極端な開きがあるのは、それぞれの国の小麦事情も影響しています。
中国は小麦については、基本的に自給自足です。世界の年間小麦生産量6億㌧の内、最大生産国は中国の1億㌧ですが、それはすべて自家消費です。つまり中国には港に隣接した大きな製粉工場もあるものの、未だに主体は内陸部に点在する小規模製粉工場です。それとは対照的に韓国には小麦畑は存在せず、100%輸入に頼っています。その結果、製粉工場は全て11の臨海工場に集約されてしまいました。
では現在日本の事情はどうなっているかといえば、内麦比率(国産小麦)は10~15%で、80%以上は米、加、豪からの輸入に頼っています。昔は内麦主体でしたが外麦(輸入小麦)が増えるに連れ、内陸中心だった製粉工場も臨海型が主力になりました。外麦が増えた理由は、生産コストの違いです。1kgの小麦を生産するのに、内麦は150円に対し、外麦は僅か20円程度で両者には約10倍の開きがあります。これは狭小な地形の多い日本はどうしてもコストが高くつくからです。もちろん小麦を自由化すると、内麦はひとたまりもないので、輸入した外麦を高く売り、その利ざやで内麦の補助金を捻出しています。
つまり日本においての小麦価格は市場原理だけではなく、人為的要素も加わり決定されていて、詳細は省略しますが、これが中小製粉がまだかろうじて存続できている理由のひとつにもなっています。もし日本で小麦の補助金を打ち切れば、内麦は壊滅し、すべて外麦だけになってしまいます。そうなると韓国型になるのは時間の問題です。このように製粉工場の集約化は、それぞれの国の小麦事情と農業政策とが複雑に絡みあっています。そして現在、日本の小麦政策は戦後最大の大転換期を迎えています。