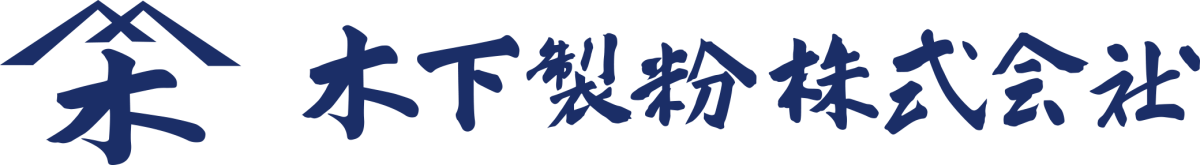#980 3か月でマスターする古代文明・・・コムギと雑穀が伝播した時期
 遠い昔に学校で習った古代文明は、「四大文明」つまりメソポタミア、エジプト、インダス、中国の4つでした。しかし近年は、発掘技術や分析方法の進歩により、従来の文明像を塗り替える発見が相次いでいます。たとえばトルコ南東部の乾いた大地に出現した巨大建造物「ビョベックリ・テペ」遺跡は、紀元前9000年、つまり今から1万1000年も昔に狩猟採集民たちによってつくりあげられました。つまり四大文明よりもずっとずっと古いのです。
遠い昔に学校で習った古代文明は、「四大文明」つまりメソポタミア、エジプト、インダス、中国の4つでした。しかし近年は、発掘技術や分析方法の進歩により、従来の文明像を塗り替える発見が相次いでいます。たとえばトルコ南東部の乾いた大地に出現した巨大建造物「ビョベックリ・テペ」遺跡は、紀元前9000年、つまり今から1万1000年も昔に狩猟採集民たちによってつくりあげられました。つまり四大文明よりもずっとずっと古いのです。
古代の新発見に興味がある方は、このシリーズ本を読んでいただくとして、ここではコムギや雑穀などの伝播に関する新発見を簡単に説明します。内容は第7回「中央アジアシルクロードの原点を探る」の中に登場します。
私たちの主食であるムギやコメ、そしてキビやアワなどの雑穀は、それぞれ異なる場所に起源をもっています。ムギは紀元前9000~6000年頃、西アジアのメソポタミア地方で栽培が始まりました。イネは中国南部の長江流域で紀元前8000~5000年頃に、そしてキビやアワは、中国北部の黄河流域で同時期に栽培化されました。そしてこれら3つの穀物は、時間をかけてユーラシア大陸全体に広がっていきました。
しかしそれぞれの広がり方には違いがあります。従来の研究では、ムギの方が最初に西から東へ伝わり、遅くとも紀元前2500年以降には中国に到達。一方、雑穀の西への到達は紀元前1500年以降とされていました。またイネについては、紀元前1500年頃に中国からインドへジャポニカ種が伝わりました。つまり「雑穀の西への伝播は、ムギの東への伝播よりもずっと後」という考え方が従来の主流でした。
 ところがこの常識を覆す発見がありました。舞台は、カザフスタン南東部の山間部にある小さな牧畜キャンプ跡、ペガシュ遺跡です。ここで発掘された紀元前2500年頃の地層から、ムギと雑穀が同時に出土しました。これは従来の想定よりも約1000年も早い時期に、「西アジア起源のムギ」と「東アジア起源の雑穀」が同じ場所で、しかも牧畜民の生活の中で利用されていたことを示す大発見でした。
ところがこの常識を覆す発見がありました。舞台は、カザフスタン南東部の山間部にある小さな牧畜キャンプ跡、ペガシュ遺跡です。ここで発掘された紀元前2500年頃の地層から、ムギと雑穀が同時に出土しました。これは従来の想定よりも約1000年も早い時期に、「西アジア起源のムギ」と「東アジア起源の雑穀」が同じ場所で、しかも牧畜民の生活の中で利用されていたことを示す大発見でした。
この発見により栽培植物の伝播は西からのムギが先行したのではなく、東西双方向からの伝播であったことがわかりました。また従来は別々のものと考えられていた「定住農耕」と「移動牧畜」が、実際は重なり合っていたという事実です。牧畜民はムギや雑穀の種子を携えて家畜とともに移動し、それを食糧や次の栽培のために活用していたのです。ペガシュ遺跡は、山間の交通の要衝に位置し、ここを通りムギは東へ、雑穀は西へと広がっていったと考えられています。
このように植物の痕跡から人類の農耕の歴史や社会のあり方を探る学問は「植物考古学」と呼ばれています。通常であれば植物などの有機物は分解されてしまいますが、火に当たって灰になったものは、数千年、数万年経っても残り続けます。この「炭化種実」を調べることで、古代の人々がどんな植物を利用していたかがわかるのです。実際は、発掘現場の土を水に入れてかき混ぜると、比重の小さい炭化物が浮上するので、そこから種実を選別して記録します。この技術を「フローテーション(水洗選別)」といいます。
シルクロードは、紀元前114年頃に漢王朝が中央アジアに進出したことに端を発しますが、これら穀物の伝播は、それよりも少なくとも2500年も以前には始まっていたことになります。石臼は紀元前5世紀のギリシアで発明されたといわれています(#747)。一方、中国では華北平野でコムギの栽培が本格化するのは前漢時代(BC206-8)になってからです。また河北省邯鄲(かんたん)にある戦国時代(BC403-BC221)の遺跡からは、回転式石臼が発見され、その次の秦代から前漢へと経過するにつれ、発見例は多くなります(#709)。よって石臼も牧畜民によって中国へと伝播したのかもしれません。