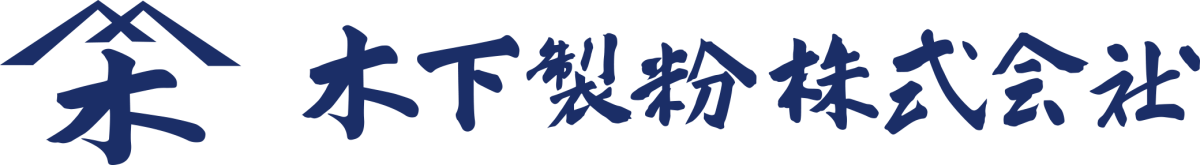#975 製粉工場見学@熊本製粉2025
 先日(2025.10.07)、熊本製粉㈱さん(以下熊本製粉)を見学させていただきました。実をいうと、今回は2017年5月に続き、2度目の訪問です。前回は熊本地震(2016.4.14、震度7強)の翌年で、液状化により破損した旧サイロの建替え工事が急ピッチで進められている最中でした。今回はその完成した保管能力6,200トンの小麦サイロの威容を目の当たりにし、圧倒されました。
先日(2025.10.07)、熊本製粉㈱さん(以下熊本製粉)を見学させていただきました。実をいうと、今回は2017年5月に続き、2度目の訪問です。前回は熊本地震(2016.4.14、震度7強)の翌年で、液状化により破損した旧サイロの建替え工事が急ピッチで進められている最中でした。今回はその完成した保管能力6,200トンの小麦サイロの威容を目の当たりにし、圧倒されました。
熊本製粉は1947年にブリジストンの子会社として発足し、2023年1月に日清製粉グループの一員となっています。前回の見学は、4階建ての「Bears技術センター」と呼ばれる研究開発棟が中心でした。この施設は、1Fはパン・菓子の研究グループ、2Fは麺・冷凍食品の研究グループ、3F は分析・品質保証部、そして4Fが講習会場及び会議室という構成で、どれをとっても私たち中小製粉業者にとっては垂涎の設備でした。そして今回は初めて中核設備となる製粉工場を見学させていただきました。以下、前回情報と併せた備忘録です(誤りがあればご容赦ください)。
年間小麦挽砕量は約7万5千トン(うち地元産シロガネコムギ1万5千トン、輸入小麦6万トン)。一般にはあまり知られていませんが、熊本県は九州では福岡・佐賀に次ぐ小麦の産地です。1日の挽砕能力(製粉能力)は400トン(3名1組×3交代制の24時間操業)。具体的には、強力用Aライン=10トン/hと中・薄力用のBライン=8トン/h、合計18トン/hの挽砕能力を備えています。
補足ですが、小麦は大きく「硬質小麦」と「軟質小麦」に分かれます。名前の通り、前者は硬く、タンパク質含有量が多いことから強力粉、後者は軟かく、タンパク含有量が中程度もしくは少ない中力粉や薄力粉になります。製粉工程は小麦の硬さに応じて微妙に異なるため、大手工場では、小麦の種類により専用の製粉ラインを設けています。つまり硬い小麦と軟かい小麦をそれぞれ効率よく製粉できるよう工夫されています。
 400トン工場ともなると、中小工場とはスケール感がまったく異なります。ロール製粉機を始め、各機械自体はどれも見覚えのあるものでも、全体としてみると同じ「製粉工場」とは思えないほどの迫力です。製粉工場は全体がラインとして連続稼働しているため、どこか1箇所でもトラブルが起きると全体がストップします。
400トン工場ともなると、中小工場とはスケール感がまったく異なります。ロール製粉機を始め、各機械自体はどれも見覚えのあるものでも、全体としてみると同じ「製粉工場」とは思えないほどの迫力です。製粉工場は全体がラインとして連続稼働しているため、どこか1箇所でもトラブルが起きると全体がストップします。
しかし、ただ単に止まるだけならまだしも、製粉工場特有の厄介なトラブルが「ライン詰まり」です。途中段階で半製品(製粉中の小麦粉)が詰まってしまうと、発見が遅れるほど、その手前側でどんどんあふれ出し、「塩吹臼」状態になります。たった1分の遅れが、30分以上の後始末につながることも珍しくありません。大工場では要所々々にセンサーを設置し、防止策を講じているはずですが、同様のトラブルはないのだろうかと、つい想像してしまいました。
余談ながら、TSMC熊本工場の稼働に伴い、県内では人手不足や賃金上昇の影響が顕著になっているそうです。特に中小企業や飲食・サービス業では人材流出や採用難、時給上昇によるコストアップが悩みの種で、熊本製粉さんも例外ではないようです。
 普段はうどん専門ですが、せっかく熊本ということで、ホテル近くの熊本ラーメンを初体験。あっさり系の豚骨スープで、「なるほど、これが熊本ラーメンか!」と納得。うどんもそうですが、麺類はやっぱりめんとつゆ(スープ)どちらの食味も大事であることを実感しました。ラーメン通を自負する東北の同業者も「なかなか、いけるね」とまんざらでもない風でした。熊本ラーメンの小麦粉は、やっぱり熊本製粉ですね。
普段はうどん専門ですが、せっかく熊本ということで、ホテル近くの熊本ラーメンを初体験。あっさり系の豚骨スープで、「なるほど、これが熊本ラーメンか!」と納得。うどんもそうですが、麺類はやっぱりめんとつゆ(スープ)どちらの食味も大事であることを実感しました。ラーメン通を自負する東北の同業者も「なかなか、いけるね」とまんざらでもない風でした。熊本ラーメンの小麦粉は、やっぱり熊本製粉ですね。