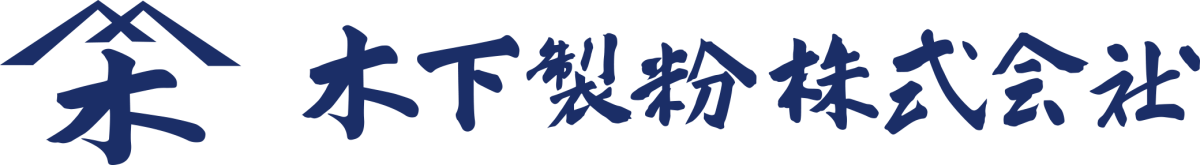#973 小麦の食物繊維大幅アップ
 妙なタイトルですが、別に小麦の品種が変わったわけではありません。実は新しい食物繊維の分析法が導入された結果、小麦に関して2つの重要な新事実が判明しました。ひとつは小麦に含まれる食物繊維が、従来よりも大幅にアップしたこと。2つ目に小麦に含まれる食物繊維は、これまで不溶性食物繊維が主体であると考えられてきましたが、実は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスが取れた腸にとって理想的な穀物であること。以下、「新しい食事摂取基準を踏まえた炭水化物・食物繊維摂取のための穀物食のあり方(青江誠一郎著、製粉振興2025年9月号No.638)」より簡単にまとめてみました。
妙なタイトルですが、別に小麦の品種が変わったわけではありません。実は新しい食物繊維の分析法が導入された結果、小麦に関して2つの重要な新事実が判明しました。ひとつは小麦に含まれる食物繊維が、従来よりも大幅にアップしたこと。2つ目に小麦に含まれる食物繊維は、これまで不溶性食物繊維が主体であると考えられてきましたが、実は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスが取れた腸にとって理想的な穀物であること。以下、「新しい食事摂取基準を踏まえた炭水化物・食物繊維摂取のための穀物食のあり方(青江誠一郎著、製粉振興2025年9月号No.638)」より簡単にまとめてみました。
従来の食物繊維の測定方法は、プロスキー変法が使用されていましたが、日本食品標準成分表七訂追補2018年以降、AOAC2011.25法による成分値に更新された結果、食品中における食物繊維量は大きく変化しました。これは従来のプロスキー変法では定量されていなかった低分子量水溶性食物繊維や不溶性食物繊維の一部であるものの定量が不十分であった難消化性でん粉を含め、AOAC2011.25法では、食物繊維の総量を定量することが可能になったからです。つまり食物繊維をより正確に測定できるようになった結果です。
詳細を述べる前に、両者の測定方法の名称の由来について簡単に説明しておきます。プロスキー変法(Prosky method)は、1980年代にカナダの食品研究者Lean Proskyらが提唱した「酵素-重量法」に基づく方法。具体的には、でん粉やタンパク質を酵素で分解した後、残渣として残る画分を「総食物繊維」として定量する方法です。それを日本で公定法として採用する際に若干の改良が加えられたので、プロスキー変法と呼ばれています。一方、後者はAOAC(Association of Official Analytical Collaboration、米国公定分析協会)が2011年に採択した第25番目の公式法であるので、AOAC2011.25法と呼ばれています。
さて両測定方法の大きな違いは、AOAC2011.25方では、これまでのプロスキー変法では定量されていなかった低分子量水溶性食物繊維や定量が不十分であった難消化性でんぷん(不溶性食物繊維)を含めて食物繊維の総量を定量することが可能となり、その結果食物繊維総量が増加しました。たとえばこめ(精白米)は、0.3g/100g→1.5g/100gと約5倍。また食パン(小麦)では、0.4g/100g→1.9g/100gと約4.8倍に増加し、小麦は食物繊維供給源として、一層重要な食材となりました(下図参照)。

特に小麦全粒粉の食物繊維含有量は、10.5g/100g→14.0/100gとなり、大幅にアップ。小麦は、これまで不溶性食物繊維が主体で、水溶性食物繊維含量は少ないとされていましたが、低分子および高分子水溶性食物繊維に富む穀類の仲間入りをしました。よってうどん、食パン、中華めんといった小麦粉製品は、食物繊維の供給源として一層重要な食品となりました。さらに小麦全粒粉は、主要穀類の中でも最も多くの食物繊維を含んでいるので、理想的な主食といえます(下図は、主要穀物に含まれている食物繊維量を乾燥重量ベースで比較)。

成人の場合、食品成分表(八訂)で栄養計算する場合は、25g/日の食物繊維の摂取が推奨されています。また1日90gの全粒穀物の摂取は、冠状動脈性疾患、心血管疾患、全てのガン、呼吸器、感染症、糖尿病、その他疾患が原因の死亡率のリスクを低下させることが、64論文のメタ解析により示されています。
特に小麦の場合、小麦全粒粉は通常小麦粉に対し、2つの大きなメリットがあります。一つは言うまでもなく、食物繊維を多く摂取できること。そしてもう一つは、同量を摂取した場合、同じ満足感(満腹感)を得られるにもかかわらず、糖質を大幅にカットできる点です。つまり自然な糖質カットが可能であるため、無理なくダイエットができることになります。