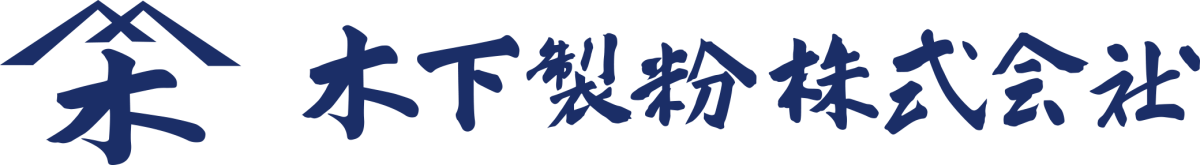#969 丸亀歩兵第12聯隊兵舎の古木
 丸亀城と県道33号線(旧国道11号)に挟まれた丸亀市大手前地区は、現在では市役所、郵便局、裁判所などの公的施設が多い官公庁街ですが、そこにはかつて「丸亀歩兵第12聯隊」が駐屯していました。1868年に明治維新となると、明治8年(1875年)5月10日に丸亀の地において丸亀歩兵第十二聯隊が編成されました。以後、聯隊は明治10年西南戦争に始まり、日清戦争、北清事変、日露戦争、シベリア出兵、第一次上海事変、第二次上海事変などに次々と出動。昭和13年9月からは満州警備の任にあたり、70年後の昭和20年8月15日に終戦を迎えます。
丸亀城と県道33号線(旧国道11号)に挟まれた丸亀市大手前地区は、現在では市役所、郵便局、裁判所などの公的施設が多い官公庁街ですが、そこにはかつて「丸亀歩兵第12聯隊」が駐屯していました。1868年に明治維新となると、明治8年(1875年)5月10日に丸亀の地において丸亀歩兵第十二聯隊が編成されました。以後、聯隊は明治10年西南戦争に始まり、日清戦争、北清事変、日露戦争、シベリア出兵、第一次上海事変、第二次上海事変などに次々と出動。昭和13年9月からは満州警備の任にあたり、70年後の昭和20年8月15日に終戦を迎えます。
 終戦後は風雨に晒され続け、荒れ果てた旧兵舎は昭和38年(1963年)4月に解体されます。弊社では当時、この解体された兵舎の木材を払い下げ、工場の増設に使用しました。鳶職人が現場で解体作業をしていると、どういうわけか屋根裏にはいくつもの銃剣や短剣が放置されていたそうです。払い下げた木材は、そのままでは使用できないので、一旦近くの神社や広場に仮置きし、そこで大工さんが削る、切るなどの加工を施した後、建設現場に持ち込み組み立てました。画像の古木は、当時払い下げた木材の一部で、表面には「丸亀歩兵第12聯隊第六中隊・兵舎建築の木材。明治八年五月八日」と記されています。現在では解体した木材を工場建設に再利用することは考えられませんが、当時は物資不足に加え、兵舎に使用されていた木材は頑丈であることから、かなりの利用価値があったようです。画像はその払下げ木材を使用しての倉庫の建設風景です。
終戦後は風雨に晒され続け、荒れ果てた旧兵舎は昭和38年(1963年)4月に解体されます。弊社では当時、この解体された兵舎の木材を払い下げ、工場の増設に使用しました。鳶職人が現場で解体作業をしていると、どういうわけか屋根裏にはいくつもの銃剣や短剣が放置されていたそうです。払い下げた木材は、そのままでは使用できないので、一旦近くの神社や広場に仮置きし、そこで大工さんが削る、切るなどの加工を施した後、建設現場に持ち込み組み立てました。画像の古木は、当時払い下げた木材の一部で、表面には「丸亀歩兵第12聯隊第六中隊・兵舎建築の木材。明治八年五月八日」と記されています。現在では解体した木材を工場建設に再利用することは考えられませんが、当時は物資不足に加え、兵舎に使用されていた木材は頑丈であることから、かなりの利用価値があったようです。画像はその払下げ木材を使用しての倉庫の建設風景です。

昭和30年代(1955~1964年)といえば、日本が戦後の復興をほぼ終え、高度経済成長へと踏み出した時代と言われています。とはいえ、まだまだ戦後を引きずっているところも多く、至るところに廃屋が散在し、丸亀歩兵聯隊の兵舎もそのひとつでした。坂出から丸亀へ向かう途中の宇多津町は、今では若者に人気の洒落た街になっていますが、当時は流下式塩田が多く並んでいた塩田の町でした。「流下式」というのは、竹枝を組んだ「枝条架」から海水を滴下させ、その間に風で蒸発させて、海水を濃縮させる製塩施設です。昭和20年代後半に導入されましたが、昭和40年代後半には、現在主流となっているイオン交換膜製塩法に取って代わられたので、その寿命は僅か20年程度と短命でした。現在の宇多津町の北部分に位置する通称新宇多津都市は、その広大な塩田の埋立地に立地しています。
またテレビ、洗濯機、冷蔵庫の「三種の神器」が家庭に広まり、日常生活が大きく変わった時期でもありました。近所のげんしゃ(お金持ち)のお家に遊びにいったときの衝撃は鮮明に覚えています。リビングにはなんとカラーテレビがどんと置いてあり、天然色には程遠い、けばけばしいカラー映像をみてびっくりしました(映像に色がついていること自体が衝撃!)。もっとも当時は、リビングという言葉も、そもそもリビングルームのある家自体も稀有な存在でした。しかもそのリビングには水冷式のクーラーが設置されていて、ひんやりとした空気がなんとも言えず快適だったのを覚えています。さらに片隅にはホームバーまで用意され、まったく意味不明の異次元空間でした。
当時の記憶に残る出来事としては、昭和39年(1964)10月1日に開業した世界初の高速鉄道、東海道新幹線があります。開業前は東京大阪間が、特急こだまで6時間30分もかかっていたのが、一気に4時間となり、翌年には3時間10分に短縮されました(ちなみに現在は2時間21分)。また1964年10月10日にはアジア初となる東京オリンピック(第18回大会)が開催されました。エチオピアのアベベ選手は、裸足で走ってマラソン優勝という快挙を成し遂げましたが、今では考えられないことです。そういえば船の体育館が竣工したのも1964年8月10日。昭和30年代とはそんな時代でした。