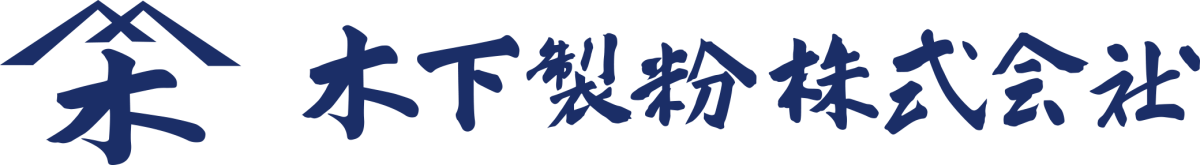#964 種類別乾麺生産量の推移@2025
 種類別乾麺生産量@2025(出典:乾麺・めんつゆ、食品新聞刊)が公表されましたので、最新版を簡単にまとめてみました。これは前回データ(1993-2022、#865)に新たに2年間分(2023-2024)が追加されたものです。まず前回の結果を簡単にまとめると次のようになります。
種類別乾麺生産量@2025(出典:乾麺・めんつゆ、食品新聞刊)が公表されましたので、最新版を簡単にまとめてみました。これは前回データ(1993-2022、#865)に新たに2年間分(2023-2024)が追加されたものです。まず前回の結果を簡単にまとめると次のようになります。
30年間に乾麺全体では、30%程度落ちていますが、特に落ち込みが大きいのがうどん(38.8%)です。うどんは乾麺の中でも特にゆで時間が長いため、その一部が冷凍うどんやLLめんに代替されたのは、明らかです。そばは93.8%とかなり健闘。ひやむぎは、個人的には大好きなので41.4%と激減しているのは理解に苦しみます。一方、干中華のように大きく伸長している(280.4%)乾麺もありますが、これは乾麺というよりも、ラーメンのひとつのアイテムとして捉えるべきかもしれません。
全体としては、需要の落ちた乾麺ですが、これは乾麺に魅力がなくなったということではありません。つまり社会が豊かになり、食品の多様化が進み、美味しい食品がたくさん流通するようになった結果です。また同じ乾麺でもメーカーによってそれぞれ個性があります。一度、色々な乾麺を試してみて、乾麺の美味しさを再認識されてみてはいかがでしょう。
さて前回から2年が経過して、改めて乾麺生産量の推移(画像参照)をみると、直近ではほぼ20万トンを回復し、下げ止まったようにも見え、この辺りが乾麺の正味の需要であると考えたいところです。繰り返しますが、乾麺の需要が下がった理由は、乾麺に魅力がないのではなく、製造・包装・流通のそれぞれの分野において技術革新が進み、食の多様化が進んだ結果に過ぎません。うどんを例にとるなら、昔は乾麺とうどん玉しかなかったものが、今では冷凍麺、LL麺、カップうどんなどの選択肢が拡がりました。

アイテム毎の推移をみると、一番目立つのが干中華の躍進です。ここ2年間で更に生産量がアップし、うどんやそうめんを一気に抜き去り、今や乾麺の中では手延めん、そばに次ぐ3番手に位置しています。30年前には乾麺中最下位であったことが信じられません。干中華は乾麺というよりも、ラーメンの1アイテムとして捉えるべきかもしれません。
30年前を基準にすると、そうめんは64.4%、手延めんは72.7%とどちらも3割前後減少していますが、今後どのように需要が推移するのか注視しています。そうめんは調理時間が短いため、うどんのように冷凍そうめんの需要はそんなに多くはないと考えます。また乾燥しない生の状態で流通する「生そうめん」も技術的には可能ですが、生そうめんでは乾燥したそうめんのシャキシャキ感が表現できないので、これもそれほど需要があるとは思えません。以前、「手延生そうめん」が商品化されたことがありましたが、最近は見かけなくなりました。多分、手間暇かかる割には商品価値が評価されなかったのが理由だと推測します。
つまりそうめんに限っては、今後も乾燥した乾麺での商品形態一択での提供になると考えます。また過去30年間において食の多様化も十分に進み、今後そうめん需要が極端に変化することはないでしょう。すると気になるのは、手延そうめんとそうめん(機械式そうめん)との棲み分けです。直近の供給量では手延そうめんが約5万トンであるのに対しそうめんは2.6万トンと約半分です。高額の手延そうめんが支持される理由は、そのツルツル食感が評価された結果です。ただ今後懸念されるのはさらなる人件費の高騰です。人件費高騰は、どちらにとっても値上げ要因ですが、手作業の多い手延そうめんは人件費比率が高く、よって今後両者の価格差はさらに広がると予想されます。そうなったときには両者の比率に変化が起こるかもしれません。