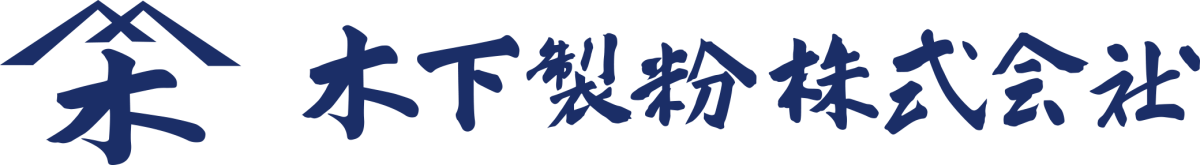#963 産地別手延そうめん生産量@2024
 社会が豊かになるにつれ食生活も多様化及び西洋化が進み、日本の伝統食である乾めん需要も減少の一途を辿っていました。しかし昨年(2024年)は生産量もほぼ20万トンを回復し、需要減少に歯止めがかかったようにも見え、この20万トンという数字が現在の乾めんの実力というか正味の需要であるようにも思えます(#952)。そして乾めん全体の中で、手延べそうめんは23%を占めているのに対し一般のそうめんは13%となっています。手延べそうめんは高価であるにもかかわらず多くの支持を得ているのは、その手延べ独特のつるつるとした食感にあります。
社会が豊かになるにつれ食生活も多様化及び西洋化が進み、日本の伝統食である乾めん需要も減少の一途を辿っていました。しかし昨年(2024年)は生産量もほぼ20万トンを回復し、需要減少に歯止めがかかったようにも見え、この20万トンという数字が現在の乾めんの実力というか正味の需要であるようにも思えます(#952)。そして乾めん全体の中で、手延べそうめんは23%を占めているのに対し一般のそうめんは13%となっています。手延べそうめんは高価であるにもかかわらず多くの支持を得ているのは、その手延べ独特のつるつるとした食感にあります。
手延べそうめんの製造は、元の生地をどんどん延ばしながら最終的に1本の細いそうめんに仕上げます。もちろん機械も導入されていますが、多くの部分においてはマンパワーが必要です。しかし昨今の人手不足に加え、製造者の高齢化が進み、どこの産地も人材確保が思うように進んでいません。また他のめん類と比較し、人件費比率が高いだけに値上げ幅も大きくなり、悩みは尽きません。
一方、一般のそうめん(機械そうめんともいいます)は、ロール製麺機で徐々に生地を延ばしなら適度な厚さになったところで、切刃(きりは)でカットされ乾燥工程へと向かいます。こちらはほぼ全ての工程が自動化されているので、手延べそうめんと比較すると製造コストは安価です。ただつるみ感は手延べそうめんの方が優位ですので、どちらを選択するかは食味・食感・価格で判断していいただくことになります。
さて「全国麺類特集2025年(日本食料新聞刊)」に手延べ素麺の産地別生産量が掲載されていたのでご紹介します。なお、手延べめんには、手延べそうめん以外にも手延べひやむぎや手延べうどんなどがあり、そういった手延べめんの総称としては「手延べ干しめん」という言葉が使用されます。また手延べそうめんは、伝統的に18kg木箱が利用されるために、生産量はこの18kg木箱が基本単位となっています。令和6年の全国生産量は、約240万箱(44,986トン)、また手延べ干しめんは、54,140トンとなっています。
①兵庫県・播州地区(全国シェア7%)
手延べそうめんといえば「揖保の糸」を連想するほど、手延べそうめん業界では圧倒的な存在感を放っています。兵庫県手延素麺協同組合では、生産者400軒で104万箱を生産。兵庫県は、組合比率が高いのが特徴で、組合外での生産は2万箱。
②長崎県・島原地区(全国シェア3%)
島原地区は組合が複数存在しているため実態把握が困難ですが、全国2位は揺るぎません。生産量60万箱に対し生産者200軒(3000箱/軒)。
③奈良県・三和地区(全国シェア5%)
三輪地区は言わずとしれた手延べそうめん発祥の地。三輪地区では、三輪素麺工業協同組合(生産者45軒)の9万箱と組合外生産の15万箱を合わせた合計24万箱を製造。
④徳島県・半田地区(全国シェア4%)
一般に手延べそうめんといえば細口ですが、半田地区だけは太口そうめんを生産しています。かつての生産量は、小豆島よりもかなり少なかったように記憶していますが、近年は一部大口製造者が生産量を押し上げています。生産者20軒に対し生産量は20箱。
⑤香川県・小豆島地区(全国シェア2%)
小豆島地区では、小豆島手延素麺協同組合(生産者63軒)の10万箱と組合外生産の2~3万箱を合わせた13万箱を生産。小豆島手延素麺協同組合のブランド「島の光」ブランドは有名です。
⑥岡山県・備中地区(全国シェア5%)
12軒の生産者で6万箱を生産。
⑦兵庫県・淡路島地区(全国シェア2%)
11軒の生産者で5000箱を生産。兵庫県といえば播州地区が有名ですが、淡路島には産地があります。